起訴の意味|起訴されたら必ず有罪?起訴後の流れを簡単に解説
起訴・不起訴などという言葉はよくテレビなどでも耳にすることが多いのではないかと思います。 言葉を聞いたことはあっても…[続きを読む]
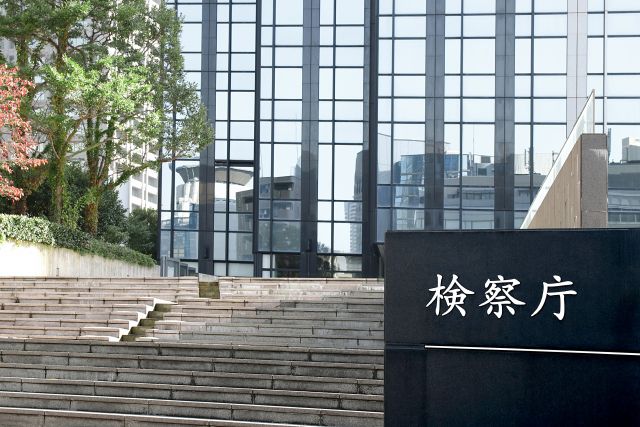
ニュースで「不起訴」や「処分保留のまま釈放」になったという報道を耳にして「不起訴ってどういう意味か」と疑問に思われたことはありませんか。
また実際犯罪を犯してしまった方は「不起訴はいつ決まるのか?いつわかるのか?連絡は来るのか?」と疑問を感じているかもしれません。
この記事では、犯罪が発生してから起訴・不起訴の処分が決まるまでの刑事手続きの流れや、不起訴処分とはどういうものなのかについてわかりやすく解説します。
ご自身やお知り合いが警察で事情聴取を受けるなどして、今後どうなってしまうのか不安に感じておられる場合でも参考になる内容となっていますので、ぜひご一読ください。
目次
まず、簡単に不起訴とはどういうことなのかについて解説します。
罪を犯して逮捕された場合であっても、ドラマで良く見るような刑事裁判を必ず受けることになるわけではありません。
「検察官」が捜査の結果集まった証拠を吟味して、刑罰を受けさせる必要があると判断した事件だけを「起訴」し、それ以外の事件は「不起訴処分」とするのです。
ここで言う検察官というのは、警察のように自ら捜査を行うこともあれば、刑事裁判を受けさせるか否かを決める権限もある、刑事手続きの中核を担う存在です。
検察官が事件を起訴すると、裁判所の法廷で刑事裁判を受けたり、書類審査で罰金刑に処せられたりすることになります。
一方、検察官が不起訴処分とした事件は、刑事事件としては終了します。
なお、不起訴処分となる理由やその種類、タイミング等については、後の章で詳しく解説します。
犯人と疑われて「逮捕」された場合、一般的な刑事手続きは次のように進みます。
なお、ここで言う「勾留」とは、裁判官が証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合に認められる身柄拘束の処分です。詳しくは下記のページを併せてご参照ください。
また、逮捕されず在宅のまま捜査が行われることもあります。
その場合は、捜査の必要に応じて警察署や検察庁への出頭を求められ、取り調べを受けることになります。その後、証拠が集まった段階で起訴または不起訴の処分が決まります。
なお、警察署・検察庁への出頭を求められるタイミングは、事件によって異なります。
勾留されている場合は、勾留期間の節目になる「10日目」または「20日目」に処分が決まることがほとんどです。
勾留中に不起訴処分が決まった場合、留置場の職員から「不起訴になったから釈放する」と告げられて、不起訴処分になったことを知ることになります。
なお、次のような場合には「処分保留のままの釈放」をされることもあります。
なお、勾留されている被疑者について詳細な精神鑑定を行う必要がある場合は、勾留を中断して鑑定留置という処分がなされ、専門医による詳細な鑑定を待つことになります。
一般的に鑑定留置の期間は2か月程度とされることが多く、鑑定留置が終了すると改めて「残存する勾留日数で捜査」を行う流れになります。
また、逮捕・勾留している事件では原則として23日間で捜査を終える必要があるのに比べ、在宅のまま捜査をしている事件ではそのような制約がありません。
したがって、後者の場合は処理に時間がかかる傾向があるようです。
また、被害者との示談を考えている方は、下記ページが詳しいので併せてご参照ください。
不起訴処分になった旨の通知は、口頭や電話での連絡で告げられるのみです。
「不起訴処分告知書」を交付してもらうこともできますが、本人や被害者のプライバシーに関わる内容が記載された書類なので、本人が検察庁で手続きをとる必要があります。
なお、被害者や告訴をした人などは、希望すれば検察庁から処分結果の通知書を送ってもらえます。
不起訴処分には検察庁内部で定められた20種類の類型*があります。事例が多い不起訴処分の類型について解説します。
*事件事務規程75条より
http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
「犯罪に当たらない」とは、捜査を尽くした結果、次のような事実が明らかになった場合をいいます。
例として「過失が問題となる事例で過失が認定できないケース」、また「法律により処罰しないと規定されている次のような場合」がこれに当たります。
真犯人が明らかとなった場合や被疑者が事件とは無関係であることを示す証拠が発見された場合(アリバイの成立など)は、「嫌疑なし」となります。
上述した「罪とならず」や「嫌疑なし」で不起訴となれば、無罪の言い渡しを受けたのと実質的に等しいと思われるかもしれませんが、実際はやや異なる面があるため、注意が必要です。
詳しくは後述致します。
刑事裁判で有罪となるには、下記の証明が必要です。
これらは裁判所に判断を誤らせないための刑事裁判における鉄則なのです。
有罪判決を得られるだけの証拠がないと検察官が判断すれば、「嫌疑不十分」として起訴を行わないのが通例となっています。
犯罪の類型の中には被害者の意思を刑事処分に反映させる趣旨から、告訴がなければを起訴することができないと規定されているものがあり、それを「親告罪」と呼びます。
また「告訴」とは、犯罪被害に遭ったという申告に加えて、犯人を処罰してほしいという積極的な意思表示です。
親告罪の場合、捜査中に告訴がされなかったり、告訴が取り消されたりすると「親告罪の告訴の欠如」や「親告罪の告訴取消し」 として不起訴処分となります。
親告罪の例としては、下記のようなものがあります。
2018年版犯罪白書によれば、検察庁が受理した事件のうち「起訴」された人員は約3割程度、また半数以上が「起訴猶予」となっている実態が明らかになっています。
起訴猶予とは、簡単に言うと下記のとおりです。
起訴猶予については、下記ページが詳しいので、併せてご参照ください。
不起訴処分と無罪は内容・効果が同じではありません。
不起訴処分の効果を無罪判決との違いと対比しながら、下表にまとめました。
| 不起訴処分 | 無罪判決 | |
| 再捜査されることは? | 新たな証拠が発見された場合などは再捜査されることがある | 憲法の規定(一事不再理)により再捜査できない |
| 判決や処分が変更されることは? | 再捜査により覆ることがある。 また検察審査会が2度「起訴相当」の議決をすれば強制起訴となる |
無罪判決を覆らせる手段はない(再審もできない) |
| 補償を求めることはできる? | 被疑者補償規程があるが、補償のハードルは極めて高い | 身柄拘束に対する刑事補償がある |
| 名誉回復の手段は? | 特にない | 刑事補償決定が確定した場合は、官報や新聞に決定要旨の掲載を求めることができる |
上表のとおり、不起訴処分には、確定判決のようにのちの判断を拘束する効力はなく、あくまで「暫定的な処分」といえます。
つまり、時効により起訴される可能性がなくなるまで、再捜査や起訴は法的に不可能ではありません。
ただ、いったん不起訴処分になって「再起」される事件は数としてはかなり少ないです。
検察官の不当な不起訴処分を抑制するために検察審査会という機関が地方裁判所内に設けられています。
ここで、不起訴処分に不服がある被害者などは審査の申し立てをすることができます。
検察審査会は市民からくじで選ばれた11人で構成され、不起訴処分の相当性を審査し、「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」のいずれかの議決を行います。
3分の2以上の多数で2回にわたり「起訴相当」「起訴議決」の議決をした場合は、地方裁判所が選任する検察官役の指定弁護士が事件を起訴し、刑事裁判を遂行します。
裁判所の刑の言い渡しが確定した場合に前科が記録されるので、不起訴処分となった場合は、前科はつきません。
なお、前科がついてしまった場合、その種類にもよりますが、公務員、教員、弁護士、弁理士や保育士の資格取得が制限されたり、警備業や金融業への就職ができなくなったりすることがあります。
また再度、刑事事件で捜査や裁判を受けることになった場合は、前科があることで、より不利な扱いを受けることがあります。
前歴とは、主に警察が捜査の参考とするために作成・参照している警察内部の記録です。
前歴には「捜査対象」となった人や罪名、処分結果が記録されます。
つまり前科とは異なり、微罪処分や、起訴猶予となった事件についても前歴として記録されます。
また、無罪判決を受けた場合でも、捜査対象となった以上は前歴として記録が残ります。
普通に生活していく上で前歴が障害になる場面はまず考えられませんが、海外渡航の際に前科や犯罪歴の申告を求められることもあります。
不起訴処分の種類や効果について解説してきました。
日本の刑事裁判では、起訴されると99%が有罪となるといわれていますが、起訴される割合は3割程度(検察庁が受理した事件)です。
起訴か不起訴かで大きく明暗が分かれることがお分かりいただけたかと思います。
もし犯罪の嫌疑をかけられた場合は、一刻も早く弁護士に相談して不起訴となるためのアドバイスを受けることをおすすめします。