前科はつく?つかない?|逮捕・書類送検・略式起訴の場合
前科がつくと「就職できない」「解雇される」あるいは「前科がついたままの人生は送りたくない」などという理由から、前科が…[続きを読む]
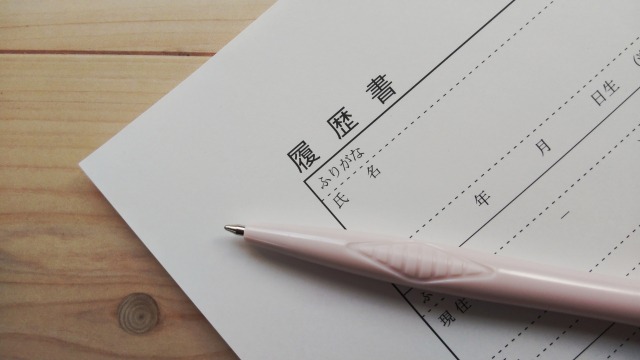
他人に最も知られたくない経歴の一つが前科などの犯罪歴ではないでしょうか。
就職や転職の際には、前科のことも履歴書に正直に書かなければならないのか、面接で聞かれたらどう答えればいいのか悩まれるかもしれません。
前科がある場合、一定の資格や職業については欠格事由とされることはありますが、それ以外では前科により就職ができないということはありません。
これはあくまで法律上の話ですが、実際に就職や転職の際に前科はどのような影響があるのでしょうか。
の順に解説します。また、家族や親など身内に前科者がいたら就けない職業や資格はあるのか等も解説致します。
前科については、下記記事も詳しいので併せてご参照ください。
一般的に犯罪歴として認識されている前科や前歴とはどういうものなのかについて抑えておきましょう。
個人が罪を犯した経歴のことを、前科、前歴、犯罪歴などということがあります。
ただ、就職の際に問題となる可能性があるのは、前科のみです。
前科は、刑事裁判手続きで「有罪となり刑を言い渡された履歴」と定義されます。
刑の言い渡しは、裁判所の法廷で行われる刑事裁判や、書面審理で罰金刑などに処せられる略式手続きのいずれかにより行われます。
前歴とは、警察の犯罪捜査の対象となった履歴のことです。
犯罪の発生から、裁判所で有罪と判断されて前科がつくまでの大まかな刑事手続きは、
という流れになりますが、前歴は「①で容疑者として捜査対象となった段階」で記録されます。
そもそも前歴は、容疑者とされた人の顔写真や指紋などとともにデータベース化されたもので「捜査資料としての性格が強い」ものといえます。
前歴が問題となるのは、あくまで刑事手続き内のことであり、就職や転職など社会生活において前歴が影響することはまず考えられません。
前科や前歴は、事実としてはなくなることはありません。
もっとも、前歴は捜査資料としての意味しかなく、記録が残り続けたとしても罪を犯して警察のお世話にならない限り不利益を被ることはありません。
しかし、前科の場合は資格や職業の制限という実際上の不利益があり、いつまでその制限を受けるのか気になるところです。
刑法では、刑の言い渡しを受けた場合でも、次のとおり一定期間経過するとその効力が消滅することとされています。
①禁錮・懲役の実刑
刑の執行終了(満期)からその後犯した罪により罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過したとき(刑法34条の2第1項)*
※懲役刑などの一部の執行が猶予された場合は、実刑部分の刑の執行終了が起算日となる(刑法27条の7)
②懲役刑などの執行猶予
執行猶予が取り消されることなく猶予期間が経過したとき(刑法27条)
③罰金以下の刑
刑の執行終了(罰金を納付した日など)からその後犯した罪により罰金以上の刑に処せられることなく5年が経過した場合(刑法34条の2第1項)
これの期間が経過すると、法律上前科はなくなります。
もちろん、就職などの際に「前科はない」と申告しても問題はありません。
少年のとき(20歳未満―2022年4月以降は18歳未満)に犯した罪の前科は、資格や職業に関する制限が緩和されます(少年法60条)。
犯行時に少年であった場合は、5年または10年、または執行猶予期間の経過を待つことなく、資格取得などの制限がなくなります。
なお、家庭裁判所による少年院送致や保護観察などの保護処分はそもそも前科ではないため、資格の制限などは受けません。
前科により制限される主な資格や職業は次のとおりです。
| 職種・資格の例 | 影響がある前科の 刑種 |
影響を受ける期間 | 根拠法令 | 備考 | |
| 罰金 | 禁錮・懲役 | ||||
| 裁判官・検察官・弁護士 | 〇 | 裁判所法46条、検察庁法20条、弁護士法7条 | |||
| 医師 | 〇 | 〇 | 医師法4条 | 「免許を与えないことがある」 | |
| 教員 | 〇 | 学校教育法9条 | |||
| 保健師・助産師・看護師 | 〇 | 〇 | 保健師助産師看護師法9条 | 「免許を与えないことがある」 | |
| 歯科衛生士 | 〇 | 〇 | 歯科衛生士法4条 | 「免許を与えないことがある」 | |
| 国家公務員・地方公務員 | 〇 | 刑終(※)まで | 国家公務員法38条、地方公務員法16条 | ||
| 取締役・監査役・執行役 | 〇(実刑 のみ) |
刑終まで | 会社法331条1項など | 一定の罪は刑終2年経過 | |
| 公認会計士 | 〇 | 刑終3年経過 | 公認会計士法4条 | 金融商品取引法違反の罪などの場合は「刑終5年経過」 | |
| 司法書士 | 〇 | 刑終3年経過 | 司法書士法5条 | ||
| 行政書士 | 〇 | 刑終3年経過 | 行政書士法2条の2 | ||
| 税理士 | 〇 | 刑終3年経過 | 税理士法4条 | 前科が特定の租税犯罪であれば「刑終5年経過」 | |
| 警備員、警備業 | 〇 | 刑終5年経過 | 警備業法3条、14条1項 | ||
| 生命保険募集人、代理店 | 〇 | 刑終3年経過 | 保険業法279条1項 | ||
| 保育士 | 〇 | 刑終2年経過 | 児童福祉法18条の5 | ||
| 建築士 (一級、二級、木造) |
〇 | 刑終5年経過 | 建築士法7条など | 5年経過後も「免許を与えないことができる」 | |
| ※「刑終」とは、刑の執行を終わるか、執行を受けることがなくなることをいいます。 | |||||
実際に再就職などの場面で前科がどのように影響するのかについて解説します。
前科や前歴に限らず、思想信条など職務の遂行や能力に関係ないような個人情報を自発的に明らかにする義務はなく、回答を強制されることもありません。
しかし職種によっては、交通規範を守る人か、金銭の管理を任せても大丈夫か、などという観点で前科の有無に関心を持たれることもやむを得ない面もあります。
実際に困るのは、履歴書や採用申込書に「賞罰」を記載する欄があるときと、面接で前科について質問されたときの対応ではないでしょうか。
仮に前科がある場合、①正直に申告する、②申告したくないと回答する、③申告しない、の三通りの対応が考えられます。
①と②の対応はなんら問題ありませんが、③の場合は採用・不採用の判断を誤らせる目的で虚偽の事実を申告することになってしまい、のちにバレて解雇の理由とされる可能性もあります。
なお、ハローワークでは求職者の基本的人権に配慮した公平な採用選考を推進しています。
法律上も「業務の目的の達成に必要な範囲内で」個人情報を収集することと法律で明記されており(職業安定法5条の4)、この考え方は企業でも「採用コンプライアンス」として広まりつつあります。
就職活動で前科がネックとなってしまう場合は、ハローワークを利用してみるのも選択肢の一つかもしれません。
結論から申し上げると、家族や親、親戚など身内に前科持ちの人がいたとしても、その不利益が本人に及ぶことはありえません。
ということで、就けない職業はありません。
そもそも、家族などの属性は、本人の責任や能力とは無関係であり、そのようなことを質問すること自体が採用コンプライアンスに抵触すると考えられています。
仮に採用面接で家族などの前科について質問されることがあった場合は、法令順守の意識が低い企業と考えられますので、注意が必要でしょう。
前科や前歴の情報はどこでどのようにして管理されているのでしょうか。
公の機関で管理されている情報とインターネット上に存在する情報について解説します。
刑事裁判手続きで刑の重さや処分を決めるに当たって、罪を犯した人の前科・前歴の有無やその内容は重要な要素となります。そのため、刑事事件の捜査や訴追を担う検察庁では、裁判所で刑が言い渡された刑を犯歴(前科)としてデータベース化して運用しています。しかし、検察庁が保有する前科に関する情報は一般に向けて公開されることはなく、内部の規程により取り扱い方法が厳密に定められています。そのため、前科の情報が検察庁から漏れることはまず考えられません。
市区町村役場でも前科に関する情報を保有しています。これは選挙資格の調査という目的のために行われるもので、一般に向けて公開されるものではありません。かつて、弁護士の要請に基づいて弁護士会が個人の前科の内容を照会し、役場がこれに回答したことが問題になった裁判があり、最高裁は次のように判断しました。市区町村役場が他の官庁などから法律に基づいて前科の内容を照会された場合は、その必要性を慎重に吟味した上で回答することが許されないわけではない前科の内容を開示することができるのは、前科の有無が訴訟で重要な争点となっており、その立証の手段がほかにないような場合に限られるこの判例のケースでは、係争中の裁判の証拠収集という漠然とした目的で照会され、それに応じたことが違法と判断されて、役場側に賠償が命じられています。このように、市区町村役場が前科の内容を開示するのは極めて限られたケースであり、民間企業の採用選考などで前科の調査に利用されることはまずないといえます。
警察が捜査対象となった人物の情報を前歴としてデータベース化しているのは前章で解説したとおりです。これも捜査や刑事手続きに限って使用されるものであり、一般に公開されることはありません。
インターネットのニュース記事やSNS、掲示板などに事件に関する情報と実名が掲載されると、検索エンジンにより容易に犯罪歴が調べられてしまいます。民間企業が採用選考をする際、応募者の犯罪歴を調べるほぼ唯一の方法は、インターネット上の情報収集ともいえます。報道機関から配信されるニュース記事は、掲載期間が1週間から3か月とされていることが多いようですが、基準はまちまちで法律による規制もありません。また、SNSや掲示板などに犯罪の情報が転載されると、管理者が削除しない限りその情報が残ってしまうのが実態です。サイトの管理者による記事の削除が望めない場合は、弁護士に依頼して法的措置により記事の削除請求をするのも方法の一つです。