痴漢に強い弁護士とは?選び方のポイントを詳しく解説!
もし痴漢容疑(迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪)で逮捕されてしまった場合、弁護士の支援を受ける必要があります。 逮捕…[続きを読む]
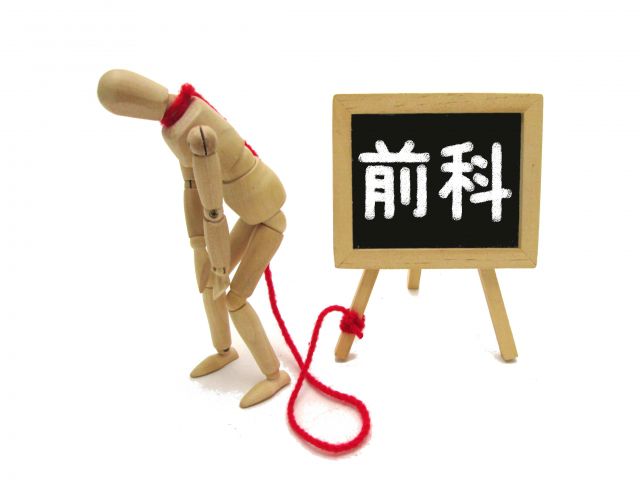
前科がつくと「就職できない」「解雇される」あるいは「前科がついたままの人生は送りたくない」などという理由から、前科がつくのを避けたいと考える方も多いのではないでしょうか?
では、前科はどのタイミングでつくのでしょうか。
この記事ではこうした疑問にお答えしていきます。この記事を読めば前科に関する不安を解消していただけると思います。
まず、前科とは何か解説します。なお「前歴」との違いも併せて確認しましょう。
前科は、下記のような過程を経ることで、与えられるものです。
少し言い換えると、下記の通りになります。
*「無罪推定の原則」とは、刑事裁判で有罪とされその裁判が「確定」するまでは被疑者・被告人は無罪と推定するという刑事事件の大原則です。
つまり「逮捕」されたり「書類送検」をされただけで、前科がつくわけではありません。
前科の内容が載った書類のことを「前科調書」といいます。前科調書には、下記のような内容が記載されています。
前科調書を作成し発行できるのは検察事務官のみです。検察事務官によって厳重に管理され、警察官など特定の人からの照会に回答されます。
前科以外に「前歴」という言葉があるので理解しておく必要があります。
前歴とは「罪の疑い」をかけられた事実の証のことをいいます。
前科とは異なり、例えば「逮捕された」「在宅被疑者として出頭要請を受けた」「微罪処分となった」「不起訴処分となった」など、段階・処分を問わずつくことになります。
また、前歴のデータは検察事務官ではなく「警察官」が管理しています。データを管理している警察官が「犯歴事項照会回答書」という書類に記載し、他の警察官から照会があった場合に回答します。
なお、犯歴事項照会回答書には、下記のような内容が記録されています。
「前科調書」も「犯歴事項照会回答書」も、前科・前歴がある人が再犯した場合、罪の常習性などを証明する証拠として使われる可能性があります。
ただ、前科調書には前の刑事裁判で有罪とした内容が記録されていますが、「犯歴事項照会回答書」には罪の常習性を証明する証拠の記載がない場合もあります(たとえば、不起訴で終わった場合)。
したがって、犯歴事項照会回答書は前科調書よりは証拠として重きを置かれない(重要度がない)、という違いがあります。
前科と前歴の違いを表でまとめると以下のとおりです。
| 記録される時期 | 管理する人 | 書類 | 証拠の力 | |
|---|---|---|---|---|
| 前科 | 刑事裁判が確定した後 | 検察事務官 | 前科調書 | 内容によっては強い |
| 前歴 | 犯罪の嫌疑を受けた後 | 警察官 | 犯歴事項照会回答書 | 前科調書よりは弱い |
刑事事件において前科がつくまでの流れは以下のとおりです。
流れとしては、まず警察の捜査が始まります(①~②)。
逮捕されない場合(「在宅事件」と言います)は、警察での取調べを受けたのち事件は「検察庁へ送致(送検)」されます(書類送検③)。
逮捕された場合(身柄事件の場合)は、逮捕から48時間以内に送検、送検から24時間以内に勾留請求され、請求が許可されれば勾留、つまり警察の留置場に留まることになります(⑥~⑦)。
なお、軽い罪の場合や弁護士を通して被害者と示談した場合などは、警察署から「釈放」される場合があります。釈放された場合、「在宅事件」として引き続き捜査を受けます。
在宅事件も身柄事件も、警察・検察の捜査・取調べを受けて、最終的な刑事処分が決まります。
刑事処分が不起訴になれば、事件は終了ですが、起訴されれば刑事裁判(正式裁判、略式裁判)を受ける必要があります(⑪~)。
そして、正式裁判の場合は「懲役○年(執行猶予、保護観察を含む)」などの判決を受け、略式裁判の場合「罰金○円」のように命令を受け、「確定」したのち前科がつきます(⑮)。
なおここで言う「確定」とは、不服申し立てができなくなった状態のことをいいます。正式裁判の場合だと「控訴・上告」で不服申立てをし、略式裁判の場合は「正式裁判請求」で不服の申立が可能です。
上記のように書類送検は前科がつく前の段階のため、書類送検されただけでは前科がつきません。
書類送検同様、逮捕は前科がつく前の段階のため、逮捕されただけでは前科がつきません。
略式起訴の場合も同様で、前科がつく前の段階のため、略式起訴だけでは前科はつきません。
あくまで、刑事裁判で有罪とされその裁判が「確定」して初めて、前科がつくというわけです。
繰り返しになりますが、前科は下記の過程を経て初めて、つくものです。
したがって、前科がつくのを避けるには、①の「起訴されることを避ける」つまり、「不起訴処分」を獲得することが重要です。
不起訴処分を獲得するには具体的に何をすべきかについては、疑いをかけられた罪に対する「認否」によって異なります。
罪を認める場合は、「起訴猶予」による不起訴獲得を目指します。
起訴猶予による不起訴獲得のために有効な手段が「示談交渉」です。
被害者と示談交渉して示談を成立させ、作成した示談書(その他必要な書類)を検察官に提示することが必要です。また当然のことですが、検察官が刑事処分を決める前に提示する必要があります。
なお、事件が立件・検挙される前に示談できれば前科がつかないことはいうまでもありません。
つまり、ただ示談をするのではなく、「迅速に」被害者と示談交渉することが重要です。
もっとも、加害者が被害者と「直接」示談交渉することはできません。
そもそも被害者の個人情報を把握している警察が加害者に被害者の個人情報を教えることはないからです。
仮に加害者自身が把握していたとしても、直接交渉を図ると警察に通報されて逮捕されたり、示談交渉そのものが決裂してやり直しができなくなるおそれも出てきます。
示談交渉は必ず刑事事件に強い弁護士に相談し依頼する必要があります。
罪を認めない場合は、示談交渉ができないので、嫌疑不十分による不起訴獲得を目指します。
この場合は「被疑者の言っていることが合理的で自然だ」等の被害者や目撃者の供述や、提示されてる証拠に不合理・不自然な点があることを指摘して「起訴するには証拠が足りない」「起訴したとしても無罪となる」等という内容を含んだ意見書を提出する必要があります。
ただ示談交渉をして不起訴を獲得するよりも、難易度が高いと言えます。
前科は刑事裁判(正式裁判、略式裁判)で懲役、罰金の刑を科され、その裁判が確定した後につきます。
解説してきたとおり、刑事裁判前の「逮捕」「書類送検」「略式起訴」されただけでは前科はつきません。
その後の流れによって刑事裁判を受け、その裁判が確定して初めて、前科がつきます。
立件・検挙された後、前科がつくのを避けるには不起訴処分を獲得することが必要です。
被害者や各種機関(警察、検察、裁判所)への対応は刑事事件に強い弁護士に任せましょう。