刑事事件の「嘆願書」の書き方、書式、効果について
刑事事件で逮捕されてしまった場合には、被害者に「嘆願書」を作成してもらうことが重要です。なぜ重要かというと罪の処分が…[続きを読む]
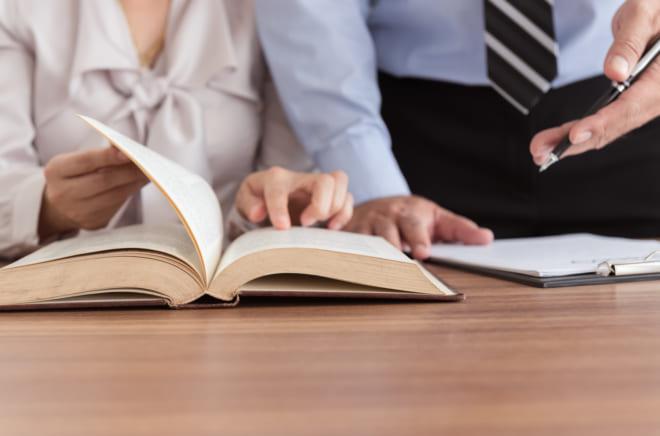
盗撮・痴漢などをしてしまい被疑者(加害者)となってしまったら、事件を起こしてしまったことについて真摯に反省をすることは勿論、被害者に対して謝罪をし、配慮することが大切です。
これは人として当然のことですが、実は、被害者が謝罪を受け入れ「示談」に応じてくれれば、処分(刑罰)内容にも影響が出ます。
さて、示談交渉をするにしても、被害者に対する「謝罪」がまずは必要です。
被疑者が被害者に謝罪の意思を伝えるには「謝罪文」が役に立ちます。
しかし、多くの被疑者の方は、刑事事件に関する謝罪文の書き方を知らないでしょう。今回は、被害者に謝罪の気持ちを伝えて示談をするための「謝罪文」の効果と、その正しい書き方(例文)について説明します。
謝罪文とは、刑事事件の被疑者や被告人、つまり被疑者が、被害者側に対して謝罪する気持ちを伝えるための書類です。
刑事事件の被疑者は、警察の留置所に身柄拘束されていることも多く、自ら被害者に謝りに行くことはできません。
また、在宅捜査のケースでも、被疑者は被害者の氏名や住所を知らないケースがありますし、知っていても、被害者は恐怖心や怒りから「会いたくない」と考えることが多いです。
そこで、被疑者や被告人は、謝罪文を書いて弁護士に渡し、弁護士から被害者に送付してもらう必要があります。
痴漢・盗撮などの刑事事件において、そもそも加害者が謝罪文を作成することにどのような意味があるのでしょうか?
これには2つの意味があります。
第1に、謝罪の意思を表明して、これを被害者に伝えるという具体的な行為を行ったという事実が、被疑者・被告人に有利な情状となるという点です。
同じく犯行を認めていても、被害者に謝ってもいない者と、(被害者が受け入れてくれたか否かにかかわらず)ともかくも被害者に謝った者を比べれば、後者の方が、検察官・裁判官の心証が良いのは当然です。
したがって、「今さら謝ったところで、どうせ許してくれない」「示談金を払うお金もないから、謝罪文など無意味だ」と考えることは間違いです。
検察官による不起訴処分や裁判官による刑の軽減、執行猶予を受けるには、最大限できる限りの努力を惜しむべきではありません。
いくら警察官や検察官に、反省している、謝罪の気持ちがあると伝え、その旨を調書に記載してもらっても、肝心の被害者に対する行為が伴っていなければ、口先だけの反省と思われかねません。行動で示す必要があります。
第2に、謝罪文を読んでもらうことが示談交渉のスタートとなるという点です。
刑事事件で被疑者や被告人が処分を軽くしてもらうには、被害者と示談することが重要です。
捜査中に被害者と示談ができれば、検察官に不起訴処分としてもらえる可能性が高くなります。
不起訴になったら、裁判の被告人となることはもちろん、有罪判決を受けて前科がつくこともありません。
起訴されてしまった場合でも、示談ができると刑を軽くしてもらえる可能性があります。例えば、実刑相当な場合でも、執行猶予をつけてもらえる可能性が出てきます。
ただ、刑事事件の被害者は、通常被疑者に対して強い怒りを感じているものです。何の謝罪もなくいきなり示談してほしいと言われても、とうてい示談には応じてくれないでしょう。
そこで、被害者と示談する前提として、被害者に対する真摯な謝罪の意思を伝える必要があるのです。そのための書類が「謝罪文」です。
謝罪文の内容1つで、被害者が示談に応じる気持ちになるかどうか変わることもあります。また、被害者の被害感情が軽い場合などには、被疑者からの真摯な謝罪文が届くだけで満足して被害届を取り下げてくれるケースなどもあります。
そうなると、捜査も取りやめになって、刑事手続から解放されることもあります。
謝罪文を作成するタイミングは、できるだけ早い方が良いです。
通常は、弁護士がついたら、犯罪を犯したことが真実で、特に争う部分もなく、本人に反省の気持ちがあることを確認できたなら、被疑者・被告人に対しすぐに謝罪文を作成するように求めるケースが多いでしょう。
まずは謝罪文を用意して、それと共に被害者に示談の申し入れをし、示談交渉を進めていく、という流れになるからです。
先に述べたとおり、被害者側は、「まずは謝るべきで、示談交渉はその後の話だ」と考えることが大部分ですから、謝罪文を用意しないと、なかなか示談交渉を始めることもできないまま起訴されてしまうこともあり得ます。「書き方がわからない」と言って先延ばしにしないようにしましょう。
【反省文との違い】
謝罪文と似た文書として「反省文」がありますが、これらは両方とも「被疑者・被告人の反省の気持ち」を表現するための書類です。
ただ、謝罪文は、「被害者に宛てた手紙」です。つまり、犯人が被害者に対して「申し訳ありません」と謝るための書類です。謝罪文を書く場合「被害者がいる」ことが前提となっています。
これに対し反省文は、「被疑者や被告人が、単純に反省していることを書いた書類」です。反省文を書くのは、通常被害者のいない犯罪です。たとえば、覚せい剤取締法違反などのケースで「もう二度としません」などの内容の反省文を書いて、検察官や裁判所に提出するのが「反省文」です。反省文を受け取った検察官や裁判所は対応を考え直し、刑事処分を軽くしてくれる可能性が出てきます。
謝罪文を書くとき、「パソコンなどで作成しても良いの?」という疑問を持つ方は多いようです。
確かに、示談書や嘆願書の書式を作るときにはパソコンで作成してもかまいません。
しかし、謝罪文は自身が手書きすることを強くお勧めします。
その理由は、被害者の気持ちを考えればわかります。
パソコンで書かれた謝罪文が送られてきたら、実際には誰が書いたか分かりません。「弁護士が代わりに書いたのだろう」と思う被害者の方もいらっしゃるでしょう。
仮にそこまで思わなくても、パソコンで書かれた謝罪文では誠意が伝わらない恐れがあります。
謝罪文は、綺麗な文字に自信がなくても手書きで書くべきです。
いったんパソコンで下書きをしてから手書きで清書するのでもかまいませんので、誠意を持って書きましょう。
また、謝罪文を書くときには、被害者の気分を害しないように、なるべく前向きに示談する気持ちになってもらえるように、内容には十分配慮しながら作成する必要があります。
特に、言葉遣いは丁寧にしましょう。謙譲語を使いながら、丁寧すぎると思われるほど丁寧に書いて良いです。
注意点として、「反省していない加害者だ」と捉えられる可能性のあるような記載をしてはいけません。
例えば「あのとき、A様が××と言ったので、つい○○してしまった」という書き方は、読み手に「こっちが悪いのか。責任転嫁している」と思われてしまいます。
間違っても「お金さえ払ったら良い」「単に減刑してもらいたいから謝罪文を送ってきた」「自分のことしか考えていない」と受け止められるようなニュアンスになってはいけません。
例えば、「起訴されて裁判になってしまうと会社をクビになってしまい、妻子が路頭に迷うので、なんとか示談してもらえないか」というのは、被害者によっては、「正直な本音を書いているな」と好感を持ってくれる場合もあれば「自分の都合ばかり!」と反発されてしまう場合もあります。
一度書いたら、時間を開けて、何度も見直しましょう。
できれば被害者に送る前に弁護士にチェックしてもらうことがベストです。不適切な記載について指摘・アドバイスをしてくれます。これを修正してから提出できるので安心です。
謝罪文は、被疑者・被告人が被害者に率直な謝罪意思を伝えるためのものですから、「正解」というものはありません。
ただ、被害者に対し謝罪の気持ちが伝わる内容にするよう気をつけなければなりません。
被害者は、ただでさえ被疑者に対しては怒りの気持ちを持っているので、厳しい目で見てきます。不用意なことを言うと感情を逆なでしてしまうことになります。
書くべき内容を挙げると、以下の通りです。
なお、被害弁償については、示談金の具体的な金額や支払い方法などについては、慰謝料だけであればこの段階で具体的な提案を記載する場合もありますが、治療費や休業損害、物損など、個別の財産的な損害が生じている場合は、被害者側からの具体的な請求を待ってから金額の交渉に入ることになります。
以下では、謝罪文のテンプレート(例文)をご紹介します。
もちろん、このまま使用するのは誠意のある行為ではないので絶対にやめましょう。この例文を参考にして文章を自作してください。
お詫び
〇〇〇〇 様
このたびは、多大なご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
どうしても、この謝罪の気持ちをお伝えしたく、失礼ながら、もこのような手紙を差し上げることといたしました。
さらに不快な思いをさせてしまいましたら、大変申し訳ありません。今は、日々反省をしながら過ごしております。
〇〇様にご迷惑をおかけすることが明らかであるにもかかわらず、そのような簡単なことを理解せずに非常識な行動に出てしまった自分が、恥ずかしく、忌まわしく、自責の念にかられる毎日です。本件の怪我で未だ通院されていると聞き、申し訳ない気持ちで一杯です。私がこのようなことを言う資格がないことは重々承知の上ですが、どうか早期に回復されることを、心よりお祈りしております。
私としては、〇〇様へ、償いをさせていただきたいと考えております。私の当然の義務として治療費や慰謝料をお渡しさせていただきたいと強く望んでおりますので、金額やその内訳などについて、改めて、お話をさせていただければ幸いです。
二度とこのような過ちを繰り返さないことを、固く誓います。
末尾になりましたが、〇〇様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、重ねて陳謝いたします。
本当に、申し訳ありませんでした。平成〇〇年〇月〇〇日
甲野一郎 ㊞
どんなに文章が苦手な方であっても、まずはご自分で書いてみてください。何故なら、謝罪文を書くこと自体が、自分を見つめ直して反省を深める重要な機会となるからです。まずは自分だけで書いてみて、それから弁護士に添削してもらうことがお勧めです。
ただ、どうしても文章が出てこないという方もいらっしゃいます。そのような場合は、弁護士が本人の気持ちを聴き取って文章にすることもできます。それを自筆で清書すれば良いのです。
さて、示談の事実を明らかにして不起訴処分や減刑などをしてもらうためには、被害者と示談を成立させたことを証明する示談書の作成が必要です。さらに嘆願書を書いたりしてもらうのも良いでしょう。
示談書とは、被害者との示談が成立していることを証明する、被害者との合意書です。
賠償金の金額や支払い方法などが記入されている一種の契約書で、被害者にも署名押印をしてもらう必要があります。
嘆願書とは、被害者の立場から、検察官や裁判官に対し、被疑者への処分を軽くしてくれるようにお願いするための文書です。もっとも、通常は示談書の文中に「寛大な処分を望む」などの文言を記載しますので、示談書とは別に嘆願書を作成してもらうことは必須とは言えません。ただ、被害者が協力してくれるなら、被害者が処分の軽減を「強く望んでいる」ことを明らかにする証拠として提出する意味があるでしょう。嘆願書は、被害者が作成名義人となりますから、被害者に署名押印してもらわないと、成立しません。
まずは被害者に謝罪文を送付して、被害者が示談に応じる気持ちになってくれたときには、示談書や嘆願書などの書面も用意して示談に臨みましょう。
示談書や嘆願書については、以下の記事で詳しく解説しているので、是非ともご参照ください。
そして、できあがった示談書や嘆願書を検察官や裁判所に提出することにより、初めて不起訴になったり、刑罰を減軽してもらえたりする可能性があります。
謝罪文は、示談書や嘆願書を作成するための最初の一歩である、ということを押さえておきましょう。
被害者がいる刑事事件は、被害者と示談することが非常に重要なポイントとなります。
そこで、被疑者の反省の気持ちを伝える「謝罪文」の果たす役割が大きくなります。
謝罪文をきちんと書いて、しっかりと反省していることが伝われば、被害者が示談や被害届の取り下げに応じてくれる可能性があります。
自分ではどのように謝罪文を書いて良いかわからない方、書いてはみたものの自信がない方は、弁護士に相談することで効果的なアドバイスを受けられるでしょう。
刑事事件で逮捕されてしまい、早めに釈放されたい場合や不起訴になりたい場合、在宅事件でも罰金前科を免れたい場合などには、お早めに弁護士までご相談ください。